介護食資格のメリット・現場で使える?
超高齢化社会に突入している日本では今後、介護食の需要が高まっていくことが予想されます。高齢者施設はもちろん、家庭でも介護食の作り方や調理のポイントなどを知っておくことが大事になるでしょう。
そこで取得を視野に入れたいのが「介護食資格」です。介護食資格とは介護食に関連する様々な知識を有している人に認定されるものです。
介護食資格を取得しておくことのメリットをいくつかご紹介しましょう。
介護食の基礎からしっかり学べる
介護食の資格を取得するためには当然、資格講座などを受講したり参考書などを勉強することになりますが、その過程の中で介護食の基礎をしっかり学ぶことができます。
介護食は通常の食事とは違います。通常の食事の場合は、料理を口にする人の咀嚼力(かみ砕く力)や嚥下能力(飲み込む力)を意識することはありません。
しかし介護食は基本的に食事をするのに何かしら障害や困難がある人を対象にしています。そのため食べやすさや飲み込みやすさなどを最大限考慮しなければなりません。
さらには被介護者に必要な栄養素や避けるべき成分なども熟知している必要があります。介護食は単に料理を楽しむだけでなく、安全性をより意識したものです。介護食資格を取得するならそうしたプラスαの部分を補った料理のポイントを学ぶことができます。
資格を生かして転職や就職ができる
介護に関連した仕事はたくさんあります。福祉施設での仕事や出張の介護の仕事などがその例です。介護食資格を取得しているなら、こうした職場への就職や転職を目指すうえで有利に働くはずです。
もちろん介護食以外にも介護に関連した仕事はたくさんあるので、総合的な介護関連のノウハウやスキルを身に着ける必要はあります。

しかし介護食資格を有していることで介護分野での仕事デビューのハードルが低くなるのは言うまでもありません。
家族や親戚の介護でも知識を生かせる
恐らくこれが最も大きな介護食資格の取得メリットでしょう。今や家族や親戚で介護を必要としている人はかなりたくさんいるはずです。
親や兄弟姉妹、祖父母など身近な人の介護を自宅でする場合、介護食作りの知識があるとかなり役立ちます。

介護の仕事は食事作りや食事介助だけではありません。他にも身の回りの世話がたくさんあります。
ですから介護食作りだけでもプロのノウハウを詰め込んでおくと、普段の介護の負担をかなり軽減できるでしょう。
介護食資格だけでは足りないこと
介護食資格を有しているだけで料理全般のエキスパートになれるわけではありません。
他にも学ぶべき点はたくさんあります。例えば以下のような点があげられるでしょう。
料理スキルや実技は自身で身につけて
まずは料理のスキルやセンスについては介護食とは直接関係がありません。味付けや食材のカット、下ごしらえなど料理全般に通用するスキルについては自分自身で身に着ける必要があります。
介護食を学ぶと料理全般が分かるようになるのではなく、料理全般の知識に加えて介護食のノウハウを身に着けるということです。

普段料理をほとんどしないという場合は、介護食資格の知識とは別に料理のスキルも同時に高めていく目標を立ててください。
外食中心の生活をしているのであれば、練習もかねて介護食を自宅で作ってみるなど工夫が必要です。
衛生面は自身で気をつけること
料理において衛星は非常に大切な要素です。特に夏場など食中毒がよく発生するような時期は衛生面で最新の注意を払わなければいけません。
若い体力のある人でも衛生が大事であれば、体の弱い高齢者にとってはより重要です。

調理に使う器具の衛星や食材そのものの衛生、また口腔ケアなど衛生全般については介護食作りをするか通常食作りをするかに関係なく常に気を留めるようにしましょう。
介護食の資格講座・認定試験の紹介
それでは介護食関連の認定試験や、それに対応した資格講座のおすすめをご紹介したいと思います。まずは2つの資格講座からですが、これらの講座はどれも、後述する2つの介護食資格に対応したものです。
どちらの講座もそれらの講座を同時に取得できるようにカリキュラムが構成されているので、資格が欲しい場合には非常に効率的です。それでは早速詳細を見ていきましょう。
SARAスクールジャパンの介護食資格
まず紹介するのは、女性向けの通信教育を展開している「SARAスクールジャパン」の「介護食基本・プラチナコース」です。この講座は初心者でも分かりやすい教材を使っているのがポイントです。

料理が苦手な人や、普段栄養素についてあまり意識していないという人でも介護食の基本をしっかり習得できるように、カリキュラムが分かりやすく組まれています。
さらにこの講座の大きな特徴として、2つの介護食資格を同時に取得できるという点があげられます。取得できるのは以下の2つです。
- 介護食マイスター認定試験
- 介護食作りインストラクター認定試験
これらの資格の詳細については後述しますが、どちらも民間資格ですが、取得しておくことで介護食のエキスパートであることを認定するものです。
「普段忙しくて学習時間が限られている」という人でも問題ありません。自分のペースで学習できるので、毎日30分など短い勉強時間でも無理なく受講終了できます。時間に余裕がある場合は最短2か月ほどで資格取得まで漕ぎつくことも可能です。
ちなみに本講座は基本コースとプラチナコースという2つのコースに分かれています。上位コースであるプラチナコースを選択すると、試験免除でさきほど紹介した2つの資格がゲットできるのでよりスムーズです。
詳しいカリキュラムや受講料などについては以下の公式サイトから確認してみてください。
介護食マイスターW資格取得講座
続いて紹介するのは「諒設計アーキテクトラーニング」の「介護食マイスターW資格取得講座」です。設計事務所が母体という少しユニークな通信教育会社の諒設計ですが、様々なライフワーク資格講座を開催しています。

介護食マイスター講座はそのうちの一つで、名前の通り介護食のマイスターを目指すために必要な学習ができるように構成されています。
介護食マイスター講座を受講するメリットの一つは学習期間の短さです。ある程度勉強時間に時間がさけるという人の場合、なんと最短で1,2か月で資格取得を達成することが可能です。「とにかく短期集中で資格が欲しい」という場合にこれは便利です。
初心者であっても問題ありません。諒設計では受講生1人1人に専属スタッフがつき、分からないことをメールで何度でも質疑できるようになっています。そのためつまづくことなく資格取得まで頑張り続けることが可能です。
本講座もSARAと同じく以下の2つの資格に対応したカリキュラムとなっています。
- 介護食マイスター認定試験
- 介護食作りインストラクター認定試験
講座には2種類あって、通常講座とスペシャル講座とに分かれています。スペシャル講座は通常講座よりも受講料が高くなりますが、試験免除で両資格の有資格者になれるのでおすすめです(通常講座は試験を受ける必要あり)。
まずは以下の公式サイトからより詳しい内容をご覧ください。
介護食マイスター認定試験
ここからは前述の2つの資格講座に対応している資格をご紹介しましょう。まずは「介護食マイスター認定試験」です。

この認定試験は「日本安全食糧料理協会(JSFCA)」が主催するものです。この資格を保持している人は以下のような点について一定の知識があると証明されます。
- 介護食を始めるタイミング
- 介護食の種類
- 介護食の作り方
- 食育と介護食の関係
- 状態に応じた介護食の種類
- 食事介助の手順とポイント
有資格者になれば福祉施設などでノウハウを生かすことも視野に入れられるでしょう。なお試験詳細は以下の通りです。
| 受験資格 | 特になし |
|---|---|
| 受験料 | 10,000円(消費税込み) |
| 受験申請 | インターネットからの申込み |
| 受験方法 | 在宅受験 |
| 合格基準 | 70%以上の評価 |
| 試験日程 | 以下参照 |
どこか特定の会場に行く必要はなく、在宅で試験を受けることができます。
先ほど紹介した2つの資格講座で学習を重ねた後に試験を受ければ合格率はアップします。ただしそれぞれ上位講座を選択した場合は、試験は免除されます。
試験日程に関しては以下の公式サイトからチェックしてみてください。
介護食作りインストラクター認定試験
続いて「介護食作りインストラクター認定試験」ですが、これは「日本インストラクター技術協会(JIA)」が主催しています。

有資格者になると介護食のインストラクターとして一定のノウハウを有していることを第三者的に認めてもらえます。具体的には以下のような知識を持っていることが証明されます。
- 介護食の栄養バランス
- 誤嚥性肺炎など高齢者の食事の注意点
- 必要な水分
- 高齢者の口腔ケア
- 嚥下能力に適したレシピ
- 肉や魚、野菜、卵などを中心にしたレシピ
実際の介護食レシピもマスターできる実践的な内容になっています。なお本資格の試験の詳細は以下の通りです。
| 受験資格 | 特になし |
|---|---|
| 受験料 | 10,000円(消費税込み) |
| 受験申請 | インターネットからの申込み |
| 受験方法 | 在宅受験 |
| 合格基準 | 70%以上の評価 |
| 試験日程 | 以下参照 |
介護食マイスター同様に在宅受験となります。また対応資格講座で上位コースを選択すると試験を受けなくても有資格者になれるという点も共通しています。
試験日カレンダーは以下の公式サイトからチェックできます。気軽に挑戦できる資格なのでぜひ詳細を確認してみてください。
資格保持者の体験談・口コミ
家族の介護食レシピが増えて助かった
自宅で簡易的な介護をしている者です。そこまで深刻ではなく、自分でだいたいのことはできるようですが、食事、特に塩分とか栄養素とかで気を遣うので介護食はかなり日頃から意識していました。
塩分は減らし、脂質やカリウム、マグネシウムといったものもほどほどにしつつカロリーは摂取しないといけない、そして、おいしくないとたくさん食べられないということでかなり苦労していました。
わざわざお金をかけて介護食資格に手を出したのは、今後社会的にもこうした介護の仕事はなくならないだろうということと、今現在リアルタイムで介護食の知識が必要だったからです。自分のスキルへの先行投資と、今の生活を支えてもらうために学習をはじめました。
パートをしていても学べて、自宅から遠くに行かなくても課題提出で試験の代わりになるのでトータルで考えると安く済みました。都会まで出向かないといけない、しかも、落ちる可能性があるとなると2回、3回と受験料、交通費をかけていたら無駄が大きすぎるので、こういう通信系の資格もいいなということで選びました。今の所、損はしていません。
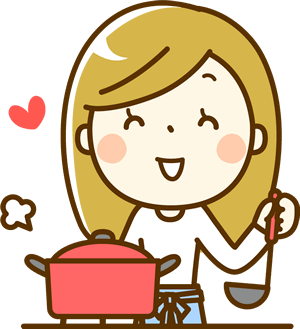
介護の仕事で作る献立が増やせた
介護食や学校給食を、依頼を受けて作っています。調理師や営業に関する免許などはありますが、介護食のレシピとなるとこれといってアピールできる部分がなく、資格を持っていればましになるだろうということと、経費をかけて税金対策にしたかったということで資格取得をしました。
日頃から介護食の製造と提供はしているのですが、メニューに幅がなく、どんなものなら食べられるのか、栄養はどうすればいいかなど調理師のスキルに追加で知識が身について、やるべきことが見えた気がします。
書籍、雑誌の情報は新鮮ですが、その時にしか使えないレシピが多く、根本的なレシピ考案や、ケースバイケースの注文に対応するのが難しいため、資格取得でカバーできてよかったです。
もちろん、流行や流行り物の影響を食事の盛り付けなどに生かせるので、雑誌系の情報も役立っていますが、資格が記載できれば何より新規営業がしやすいというメリットがあります。盛り付けは雑誌で学び、資格は営業、新規顧客への売り込みに使えています。
あとは、この資格を生かして何かもう少し得られるものがあれば良いのですが、今の所ただの肩書き止まりです。肩書き以上の国家資格のような実力につなげるには現場で自分で腕を磨いて力を証明するしかありません。





